行動変容の仕組み設計
- Weihao Hung
- 2025年2月25日
- 読了時間: 5分
人間は変化に対する不安や、現状を維持することへの安心感から、「今のままで大丈夫」「変わる必要はない」と考えがちです。その結果、行動変容が妨げられてしまいます。具体的には、以下のような認知バイアスが、新たな変化や行動を避ける要因となります。

サステナブルな行動を妨げる要因
サステナブルな行動を妨げる要因には、心理的・社会的・経済的なものがあり、以下のとおりまとめております。
1. 損失回避バイアス:人は利益を得ることよりも損失を避けることに強く反応する傾向があります。たとえば、1000円を得る喜びよりも1000円を失う痛みの方が心理的に大きく感じられるため、新しい挑戦を避けたり、リスクを取ることをためらったりします。
2. 現状維持バイアス:変化することで得られる利益よりも、現在の状態を維持することを好む傾向です。「今のままで問題ない」と考え、新しい行動を起こすのを避ける要因となります。たとえば、新しい技術やシステムの導入をためらうことがこれに当たります。
3. 投影バイアス:自分の現在の考えや感情が、将来も変わらないと過信するバイアスです。たとえば、「今、運動したい気分だから、これから毎日運動するはずだ」と考え、現実的な計画を立てられないことがあります。
4. 自信過剰バイアス:自分の能力や知識を実際よりも過大評価してしまう傾向です。たとえば、「自分ならこの問題は簡単に解決できる」と過信して準備を怠ったり、リスク管理を軽視したりする原因になります。
5. 楽観性バイアス:自分にとって都合の良い未来を想像し、リスクを過小評価する傾向です。「自分は大丈夫」「悪いことは起こらない」と考えてしまい、適切なリスク対策を取らないことにつながります。
6. 正常性バイアス:異常な状況でも「いつもと同じだ」と思い込み、適切な行動を取れなくなるバイアスです。災害時に「大丈夫だろう」と避難を遅らせる行動などが典型例です。
7. 現在バイアス:将来の利益よりも目の前の快楽や報酬を優先する傾向です。たとえば、「今は遊びたいから、勉強は後で」と考えてしまい、長期的な計画を実行できなくなることがあります。
8. 同調バイアス:周囲の人々の行動や意見に流され、自分の判断を変えてしまう傾向です。「みんながやっているから大丈夫」と考え、本来すべき行動を取らないことにつながります。
9. 確証バイアス:自分が信じている情報を支持する証拠ばかりを集め、反対意見や異なる情報を無視する傾向です。たとえば、「この商品は絶対に良いものだ」と思い込むと、ネガティブなレビューを軽視してしまうことがあります。
10. 利用可能性バイアス:記憶に残りやすい情報(目立つニュースや最近経験したこと)を重視し、確率や事実を正しく判断できなくなるバイアスです。例えば、「最近飛行機事故のニュースを見たから、飛行機は危険だ」と考えてしまうことがあります。
11. 帰属バイアス:自分や他人の行動の原因を誤って判断する傾向です。特に、他人の失敗は「その人の能力や性格のせい」と考え、自分の失敗は「環境や運のせい」と考えることが多くなります。
12. 自己奉仕バイアス:成功は自分の能力のおかげ、失敗は外部要因のせいと考えるバイアスです。たとえば、試験に合格したときは「自分の努力の成果だ」と思い、不合格だったときは「試験が難しすぎたせいだ」と考える傾向です。
13. 後知恵バイアス:物事が起こった後に、「そんなことは予測できていた」と考えてしまうバイアスです。実際には事前には予測できなかったのに、結果を知った後で「最初から分かっていた」と思い込んでしまいます。
行動変容の仕組み設計のヒント
行動変容を促すためには、以下のような仕組みを設定することが重要です。
1. 正しい情報を提供する(啓発):バイアスの影響を減らし、行動の必要性を理解させる。誤った認識や偏った情報(確証バイアス・利用可能性バイアス)を修正し、行動のメリットやリスクを正しく伝える。例:
CO2削減の具体的な効果をデータで示す
事例やストーリーを活用し、身近な問題として認識させる
2. 行動したくなる環境を整える(ナッジ):意識しなくても望ましい行動を取りやすくする。現状維持バイアスや現在バイアスを克服するために、無意識のうちに良い選択をするよう促す。例:
カーボンフットプリントの見える化で選択を誘導
省エネ行動をとると「あなたの選択が社会に貢献しています」とフィードバックを提供
3. 褒美と罰則を設定する(インセンティブ):損失回避バイアスや楽観性バイアスを克服し、行動を継続させる。行動に対して明確な報酬や罰則を設け、モチベーションを高める。例:
CO2排出削減に応じたポイント還元や割引
一定の排出量を超えると追加コストが発生
4. 選択を禁止する(強制):確実な行動変容を促すための最終手段正常性バイアスや同調バイアスを乗り越え、全体の行動を強制的に変える。例:
使い捨てプラスチックの使用禁止
一定の排ガス基準を満たさない車両の使用禁止
これらの仕組みを組み合わせることで、行動変容を促進し、持続的な変化を実現できます。
出典:竹林正樹(2023)「心のゾウを動かす方法」を基に弊社作成

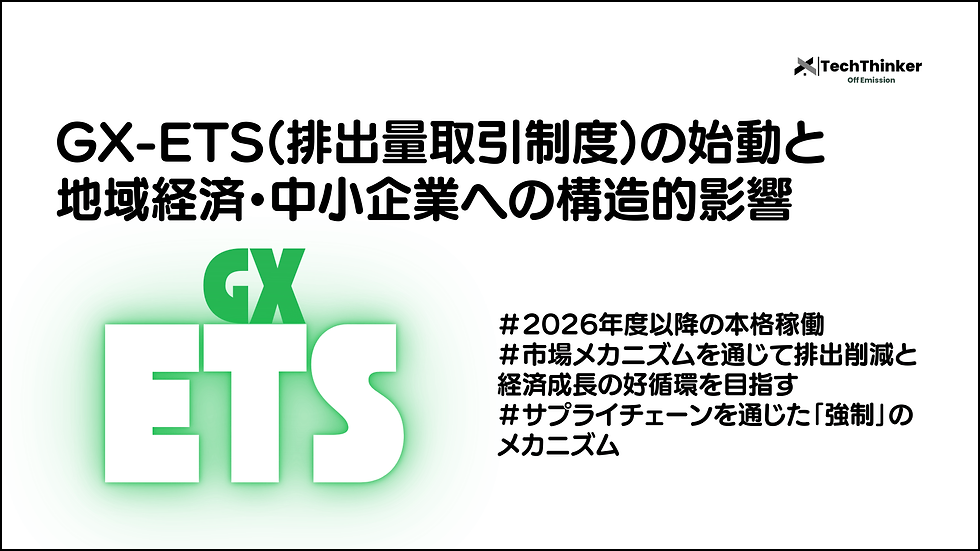

コメント